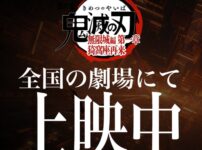「よく、これほどの深い森が、大都会である東京に残っていてくれたものだ」と思っている人が大多数と思います。実はこの深い森は、人工の森なのです。1912(明治45)年7月30日、明治天皇が崩御なされ、明治天皇を祀る神社創建の機運が生まれました。神社建設地に決定した代々木御料地は、江戸時代を通じて大名の屋敷があったところで、そこを明治になって宮内省が買い上げ御料地としました。神社建設地に決定した1914(大正3)年当時、この代々木御料地の周辺は荒地のような景観が広がっていたそうです。明治天皇を祀る神社をつくるからには、鎮守の森が必要ということで、この“ 荒地”に森を造成することになりました。林学博士の本多静六、日比谷公園の設計に携わった造園家の本郷高徳、日本の造園学の祖とされる上原敬二といったそうそうたる顔ぶれを集め、実行機関である「明治神宮造営局」が発足。森の造成計画が本格的に始まりました。計画の中心を担った本多、本郷、上原の3人が主木として選んだのは、カシ、シイ、クスノキなどの常緑広葉樹でした。もともとこの地方に存在していたのが常緑広葉樹であり、各種の広葉樹木の混合林を再現することができれば、人手を加えなくても天然更新する「永遠の森」をつくることができると考えたからです。しかし、当時の内閣総理大臣・大隈重信がこの構想に異を唱えました -----「明治神宮の森も、伊勢神宮や日光東照宮のような荘厳な杉林にすべきである。明治天皇を祀る社を雑木の藪やぶにするつもりか」と -----。本多博士らは、そもそも明治神宮の地は、関東ローム層の洪積台地にあるため保水力に乏しく、潤沢な水を必要とする杉には適さない土地であると判断していました。そこで本多博士は、東京の杉と日光の杉について樹幹解析を行い、日光に比べていかに東京の杉の生育が悪いかを科学的に説明し、大隈首相を納得させたそうです。もしこのとき説得に失敗していたら、今頃明治神宮の森は、やせ細った杉が茂るみすぼらしい森になっていたことでしょう。

森づくりは、まずこの土地にすでにある木を生かすことから始まりました。将来の主木となる、カシやクスノキなどの常緑広葉樹が育つまでには相当な時間がかかるため、それまでは今ある木々を活用していくという計画が作成されました。その計画は、「明治神宮御境内林苑計画」に四つの段階の「森づくりの工程表」としてまとめられました。第1段階は、まずは見た目として神社にふさわしい森を形づくるため、“ 仮設の森”をつくる工程-----主木として高くそびえる上冠木に、在来樹種であるアカマツやクロマツ、あるいは全国から届けられた10 万本の献木から大きなものを選んで植える。マツの間には成長の早いヒノキやサワラ、スギ、モミなどの針葉樹を植え、さらにその下に将来の主木となるカシやシイ、クスノキなどの常緑広葉樹を植える。第2段階では、林冠の最上部を占めていたアカマツやクロマツが、下から伸びてきた針葉樹に圧倒されて次第に枯れていき、数十年後には、台頭してきたヒノキやサワラなどの針葉樹が最上部を支配するようになり、在来樹種のマツは数カ所に点在するだけになる。第3段階で、やっとカシやシイ、クスノキなどの常緑広葉樹が林相の中心を占め始め、その間に、ヒノキ、サワラ、スギなどが混生し、まれにアカマツやクロマツ、ケヤキなどが見られるといった状態になる。最後の第4段階では、カシやシイ、クスノキなどが主木としてさらに成長するとともに、2世代目の木が育ち、常緑広葉樹林が広がっていく。こうして主木が人手を介さず、自ら世代交代を繰り返す「天然林相」に到達したとき、鎮守の森は完成します。現在は、第4段階の入口にきています。風土に合った自然の森を100年以上もの時をかけて完成させていくという、見事なグランドデザインです。

戦後の復興期に旺盛な木材需要を満たすため、国は建材となるスギやヒノキを大量に植える政策を取りました。しかし国産材の需要が低迷した1970年代以降、山の整備が行き届かず、今、多くの森林が荒廃の危機に直面しているうえに、現代の『花粉症』の原因にもなっています。大正初期の日本人が、当時の英知を結集してつくり上げようとした「永遠の森」。そこにあるのは、森づくりへの明確なビジョンと、100年先を見据えた壮大なグランドデザインです。本多博士をはじめとする主導者たちの情熱が、日本全国から賛同の声を呼び起こし、まさに国民運動となっていきました。その姿に現代の私たちが学ぶべきことは多いと思います。明治神宮の森は、関東大震災や戦災をも乗り越えて、今の姿があります。この森は、後世の世代が確実に引き継いでいってほしいですね。