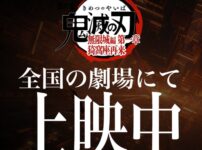マックノート彗星は2016年12月下旬になると急速に年明るくなりました。12月下旬には4等前後、2007年1月の初めには肉眼で見ることができる明るさになりました。近日点通過は2007年1月12日で、近日点距離は0.17AUと太陽に非常に接近する軌道を持っていたため、観測に適した期間は短く、薄明中の空でしか見ることができませんでしたが、非常に明るくなったため日没直後の低空でも双眼鏡で写真のような尾を引く姿を見ることができました。

近日点通過後は、南半球からでないと姿が見えなくなりました。オーストラリアの空で本格的にその雄姿を見せるようになったのは1月18日ごろからで、特に19日と20日の両夜は、日暮れ後に西よりの地平線上にくっきりと全体像が浮かび上がった。高く盛り上がるような幅広いダストの尾の光芒は、まるでオーロラか虹のようにも思え、見る者を圧倒した。明るい頭部から、ゆるやかにカーブしながら右に広がるダストの尾は、蒸気機関車の煙がドドッとはき出される様子そっくりのイメージで、はじめのうちはカメラを構えるのも忘れ、茫然として立ち尽くし見とれてしまうほどの素晴らしいものだった。近日点通過前後のころには、天頂近くで見えるオーストラリアでは、白昼に尾を引く姿が双眼鏡でもくっきり認められた。当時の様子をステラナビゲータで再現してみました。こうしてみると、よく見たものすごく大きくカーブした尾は、けんびきょう座にあり、見かけ上は意外と小さく見えていたことがわかります。


白昼の彗星で思い出されるのは、1965年の池谷・関彗星だが、10月21日に太陽表面からわずか約45万km(太陽の直径の約1/3)のところを通過し、近日点通過時には彗星が推定-17等級に達し、約60分間満月よりも明るくなったのが観測されたそうです。昼間の太陽のすぐ近くでもはっきり見え、尾が太陽の周りに巻きついているように見えたという。全体的な姿は、核が分裂し大量のダストが放出された1976年のウエスト彗星とよく似た姿となりましたが、ダストの尾の明るさではウエスト彗星の方が眼視的にははるかにクリアーだったそうです。頭部の明るさでは、20世紀で最も明るいと言われ金星なみの輝きを見せた1970年のベネット彗星の方が勝っていたそうです。青いイオンの尾は、1997年のヘール・ボップ彗星の方がはっきりしていて、マックノート彗星ではほとんど見えなかったそうです。尾の全長は、1996年の100度近くに伸びた百武彗星と比べると、40度とかなり劣る。こうしてみると、マックノート彗星はベネット彗星とウエスト彗星を足して、横に引き伸ばしたようなイメージ、というのが一番ぴったりくるかもしれない。言い換えれば、過去の大彗星の特徴のほとんどを持ち合わせた華麗なほうき星だったとも言える。